話題の本
話題の本一覧
- 「習近平」とは何者なのか?
- きみはエドワード・ウィルソンを知っているか?生物学の最重要人物に迫る
- 無駄こそが尊いという、禅の逆説的な知恵
- “人生の終盤”にドラマが炸裂!!の超短編老齢小説集
- 未曾有の強気社員はなぜ出現し、仕事に何を求めているのか
- 追いつめられる金一族、成熟しない韓国政治。またもや半島が波瀾の目に。
- 子供たちの前途を祝する書
- フランス旅行で建築を見ない人はいない。なぜならそれは歴史の証人だから
- 「明日に向かって種を蒔け!」 2000年以上前から伝わる心に刺さる不思議な名言
- 孤高の天才による、童心溢れる藝術作品
草思社ブログをご覧ください
最先端研究の成果をもとに「効果的なトレーニング」をめぐる疑問に答える!
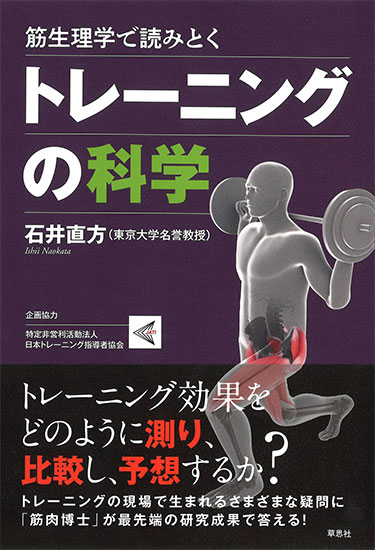
本書は「筋肉博士」として知られ、新聞・雑誌やWEB媒体を含め多くのメディアで発信を続けてきた著者が、長年の研究者としての蓄積を世に問う一冊です。
著者が筋力トレーニング(レジスタンストレーニング)をテーマに研究に取り組み始めたのは1990年ごろからですが、当時はアメリカでも、筋力トレーニングはパワー系の競技者が補助的に取り入れる程度で、コンディショニングやけが予防対策としては効果があるものの、一般人の健康づくりにポジティブな効果は及ぼさないと考えられていたといいます。
ですが、その後30年で状況は激変します。さまざまな面で骨格筋の重要性が知られるようになって、アスリートのパフォーマンス向上だけでなく、生活習慣病の予防や、高齢者の健康づくりなどの目的でも、あたりまえのように筋力トレーニングがおこなわれる時代になったのです。
多様な人たちが多様な目的で「筋肉づくり」をおこなうようになると、当然そのための方法論も多様化してくるのですが、ネットで発信される情報は玉石混交で、正しく判断するためには運動生理学やバイオメカニクスの基礎知識を身につけておく必要があります。本書はそのために打ってつけの一冊といえます。
ここ15年ほどの間に、トレーニング効果の仕組みを分子レベルまで立ち入って解明するための実験法・方法論もいちじるしく進歩して、特定のトレーニングプログラムにどんな効果があるのかを即時に調べたり、より効果的なプログラムを開発したりすることも可能になってきたと著者は書いています。
本書では筋力トレーニングのプログラムを理解するために不可欠な生理学的基礎をわかりやすく解説するとともに、トレーニングの現場で発生するさまざまな疑問の解消につながる先端的研究の成果について紹介していきます。
▽何セットおこなうのがベストなのか?
▽セット間の休息はどの程度が良いのか?
▽最適なトレーニング頻度とは?(毎日おこなってはいけないのか?)
▽筋メモリー(マッスルメモリー)とは?
――といった、筋力トレーニングをする際にぶつかる疑問についても、さまざまな研究結果をもとに考察しています。レベルや年齢に関係なく「トレーニングがある日常」を送るすべての方に、ぜひ手に取っていただきたい本です。
(担当/碇)
【本書より抜粋】
以上の研究結果をまとめると、長期効果としての「筋肥大」あるいは急性効果としての「タンパク質合成」は、ともに3~5セットくらいまでは増加し、その後ほぼ頭打ちになるということになります。それ以上おこなっても逆効果にはならないものの、さらなる効果はあまり期待されず、無駄になる可能性があります。
やはり「標準的プログラムは正しい」「経験にもとづくものは間違いなかった」ということになるのでしょう。「最適なセット数は?」と問われた場合には、ある程度自信をもって「3~5セット」あるいは「3~6セット」と答えてよいと思います。
「chapter5 トレーニング容量と筋肥大効果」より
頻度に関してはまだ不明確な点が多く残されているようです。……一方、最近の研究から、高齢者や女性を対象とする場合にはセッション当たりの容量を減らし、週4~5回まで頻度を高めるという方法の有効性が示されたことは大きな収穫でしょう。
「スクワットを1日1セット、週5日」のようなプログラムは心理的ストレスが小さく、習慣化しやすいと考えられるからです。
「chapter7 最適なトレーニング頻度」より
一般に、トレーニングによる筋肥大や筋力増加の速度はトレーニング期間とともに低下してゆき、やがて「頭打ち」になります。こうした頭打ち現象は、単に相対的強度を一定に保つ(筋力の増強とともに絶対的強度を漸増する)ということでは避けることはできません。
このプラトー状態を克服し、一段高いレベルへステップアップできるかが、長期的な視野でトレーニングが成功するかどうかのカギになるともいえるでしょう。
トレーニング効果の頭打ち現象には、少なくとも部分的にトレーニング刺激への「慣れ」にともなう感受性の低下、すなわち馴化が関与していると考えられます。そうすると、トレーニング効果が十分に現れている状態では、筋メモリーと馴化という二つの現象が筋線維内に生じていることになります。
ここで一定期間トレーニングを休止すると、筋量や筋力は減少に転じますが、筋メモリーは残存する一方、馴化は徐々に解消され再感作が生じる可能性があります。この状態でトレーニングを再開するとどうなるでしょうか。
「chapter9 長期的プログラムへのヒント」より
