話題の本
話題の本一覧
- 昆虫の顔に魅入られて。「不気味」「かわいい」、あなたはどう思うか。
- エビデンスに基づいた、画期的組織理論
- 「習近平」とは何者なのか?
- きみはエドワード・ウィルソンを知っているか?生物学の最重要人物に迫る
- 無駄こそが尊いという、禅の逆説的な知恵
- “人生の終盤”にドラマが炸裂!!の超短編老齢小説集
- 未曾有の強気社員はなぜ出現し、仕事に何を求めているのか
- 追いつめられる金一族、成熟しない韓国政治。またもや半島が波瀾の目に。
- 子供たちの前途を祝する書
- フランス旅行で建築を見ない人はいない。なぜならそれは歴史の証人だから
草思社ブログをご覧ください
ソルニットにも影響を与えた、英国稀代の批評家の傑作集
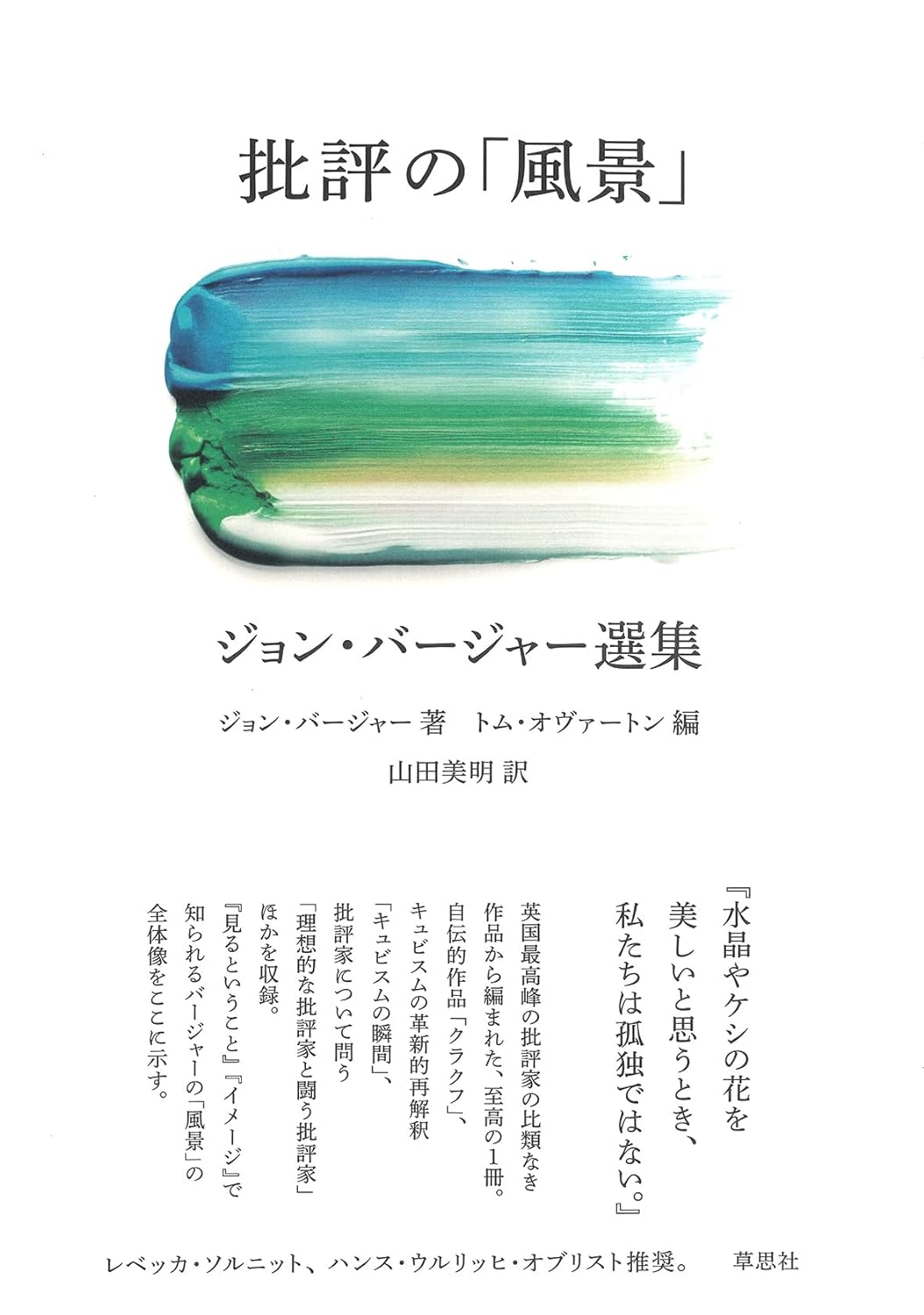
ジョン・バージャーは英国が誇る美術批評家で「イギリスのベンヤミン」などとも評されます。『見るということ』や『イメージ』などの著作で日本でも確固たる地位を確立しています。本書は、そのバージャーの思想の全体像を知るのに最適な入門かつ決定版と呼べる選集です。
「キュビスムは、キュビスムの芸術家から見れば自然発生的なものだった。私たちから見れば歴史の一部だが、興味深いことにまだ終わっていない。こうして見るとキュビスムは、様式的区分としてではなく、一定数の人々が経験した瞬間として考えるべきだ。奇妙に配置された瞬間としてである。」と、キュビスムの革新的な見方を提示する「キュビスムの瞬間」や、「肖像画は手製の靴のように当人にぴったり合わなければならないが、その靴の種類な問題になることはなかったのだ」と、肖像画に描かれる個人と社会的役割について考察した「もはや肖像画は存在しない」などの美術批評はもちろんのこと、ベンヤミンやバルトについて語った文芸批評や追悼文まで、実に幅広い作品を収めています。
現代を代表する思想家で、バージャーからも影響を受けているレベッカ・ソルニットは、本書に寄せた謝辞のなかで「情熱的で過剰に政治的でありながら、同時に芸術の創作や日常の細部にも関心を持てること」と、バージャーが矛盾しそうな態度を同時に内包し体現した批評家であることを述べています。彼がそのような視点で物事を見ていたことは、本書をお読みいただけるとよくわかると思いますが、
どのようにしてそのような視座を獲得したのかに迫るのが、冒頭に収められた自伝的エッセイ「クラクフ」です。バージャー自身についてのエッセイはこれまで邦訳書に収められておらず、貴重な一作となっています。彼には、ケンという深い仲にあった人物がいました。バージャー自身はアカデミックな教育を受けていますが、それ以上にこのケンと過ごした日々が、バージャーに複雑なものの見方を教えていたのです。
「君はきちんと理解してからでなければ文末まで読まなかった。それが君の秘訣だよ」。
良質な批評は、世界を単純化することなく見つめ考え続ける力を私達に与えてくれるものです。世界が混迷を極めていくように思えるこの時代、バージャーの批評は多くのことを教えてくれることと思います。
(担当/吉田)
目次
第一部 地図を描き直す
一 クラクフ
二 紙に絵を描く
三 あらゆる絵画や彫刻の基礎は素描である
四 フレデリック・アンタル――個人的賛辞
五 デンマークの労働者俳優への講話――観察術について(ベルトルト・ブレヒト文、
アーニャ・ロストック&ジョン・バージャー訳)
六 革命的な解体――マックス・ラファエル著『芸術の要求』について
七 ヴァルター・ベンヤミン――好古趣味と革命
八 物語の語り手
九 エルンスト・フィッシャー――哲学者の死
十 ガブリエル・ガルシア・マルケス――死の書記官が死を読み返す
十一 ロラン・バルト――仮面の内側
十二 ジョイスの潮に乗って進む
十三 ローザ・ルクセンブルクへの贈りもの
十四 理想的な批評家と闘う批評家
第二部 大地
十五 ルネサンスの明瞭
十六 デルフトの眺望
十七 ロマン主義のジレンマ
十八 ヴィクトリア朝時代の意識
十九 キュビスムの瞬間
二十 パラード、一九一七年
二十一 パリに関する考察
二十二 ソ連の美学
二十三 ビエンナーレ
二十四 現代の芸術と資産
二十五 もはや肖像画は存在しない
二十六 美術館の歴史的役割
二十七 芸術作品
二十八 『永遠の赤』(一九六〇年)の一九六八年版および一九七九年版への序文
二十九 『彼らの労働のなかへ』三部作への歴史的あとがき
三十 白い鳥
三十一 魂とその操縦者
三十二 一九九一年八月の第三週
三十三 場に関する一〇論(二〇〇五年六月)
三十四 石(二〇〇三年六月、パレスチナにて)
三十五 それまでの間
『批評の「風景」 ジョン・バージャー選集』に関するお詫びと訂正
もくじに誤りがありました。正しくは下記の通りです。
p5.第二部 大地
(誤)十五 ルネサンスの明瞭
↓
(正)十五 ルネサンスの明瞭性
お詫びして訂正いたします。
(草思社・編集部)
